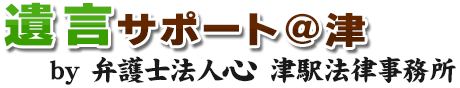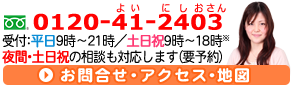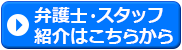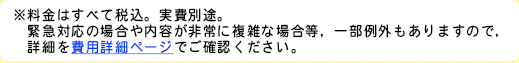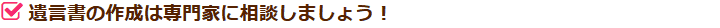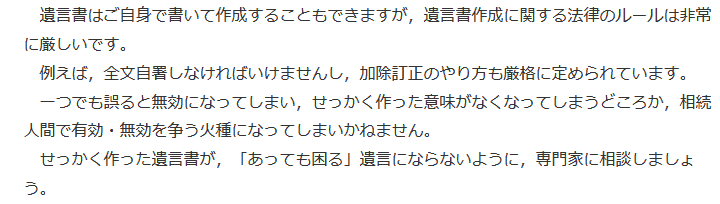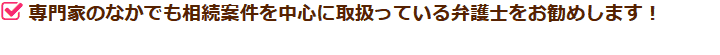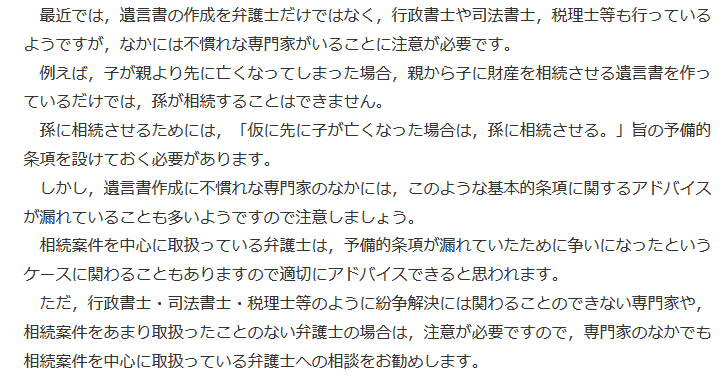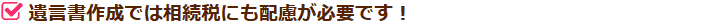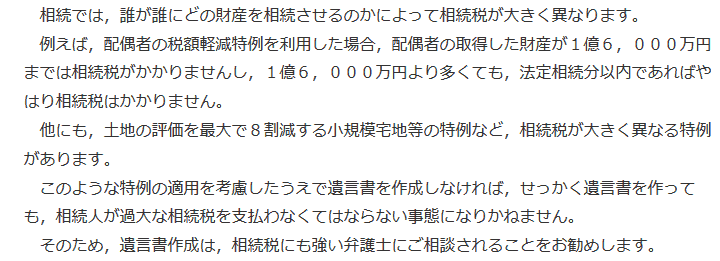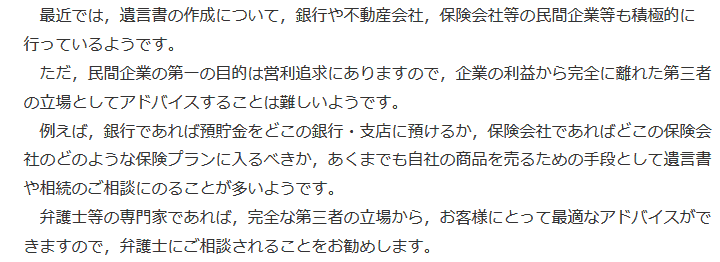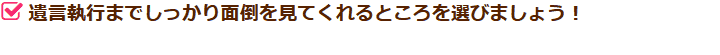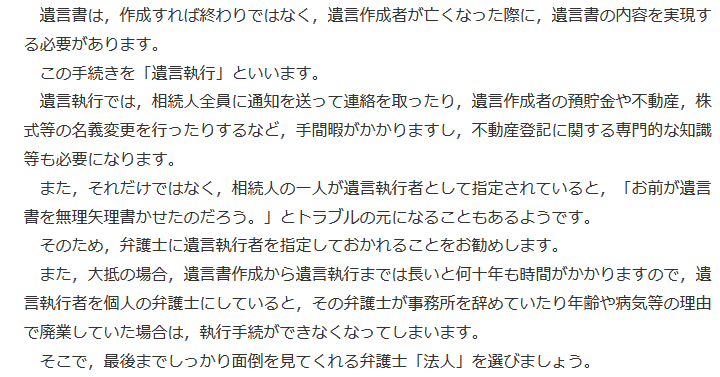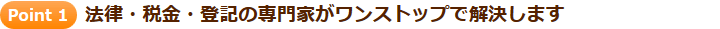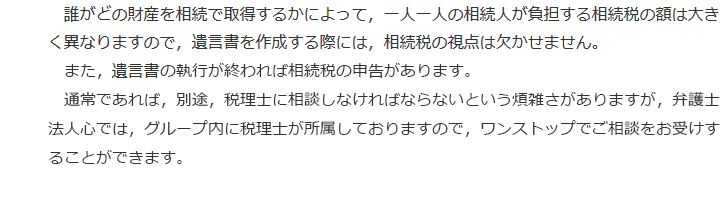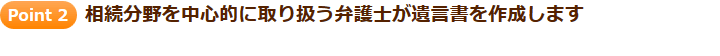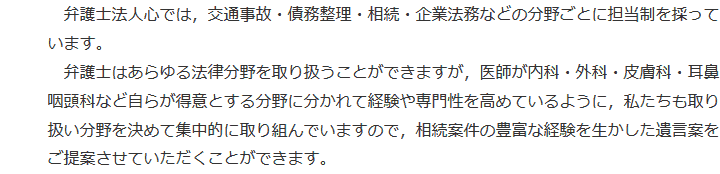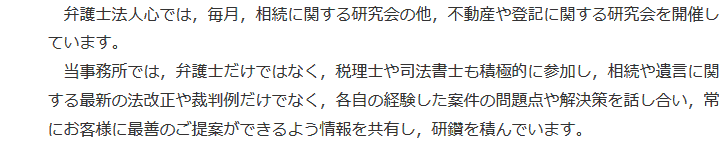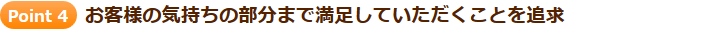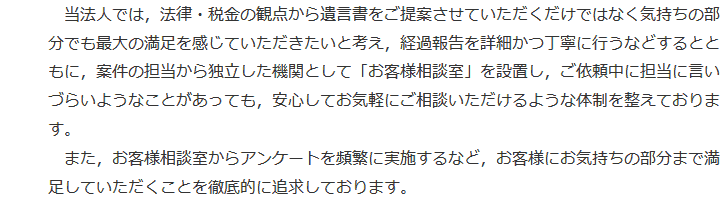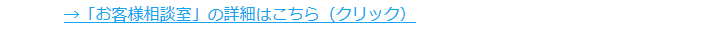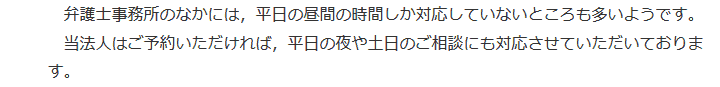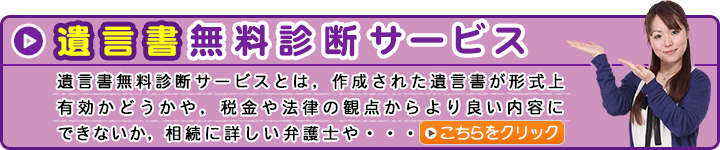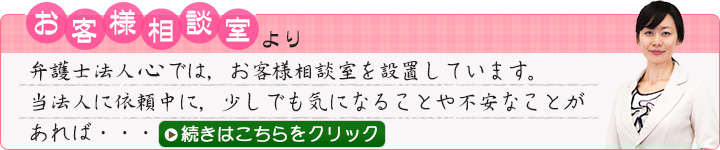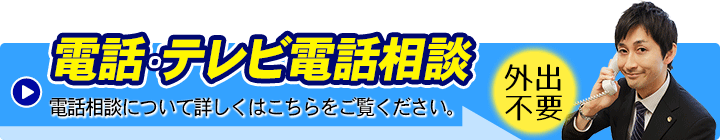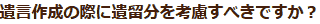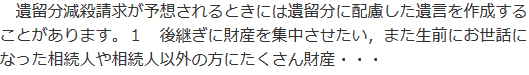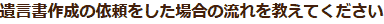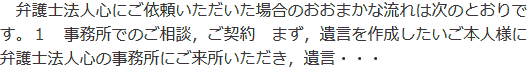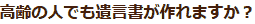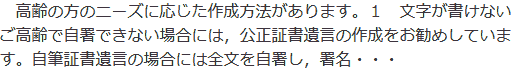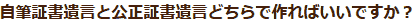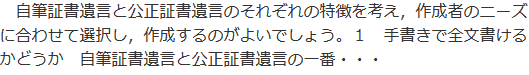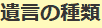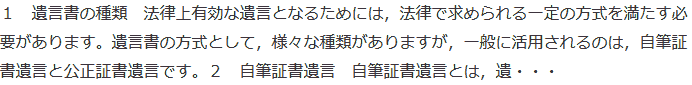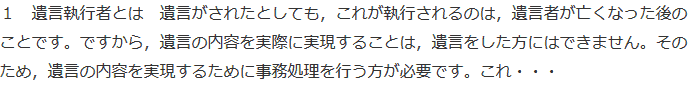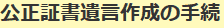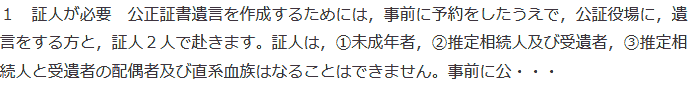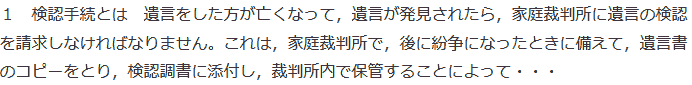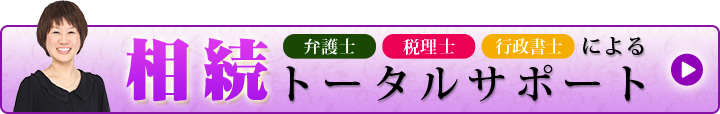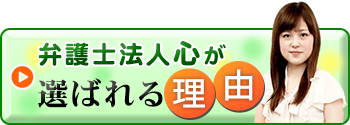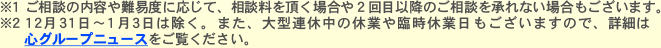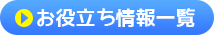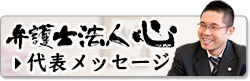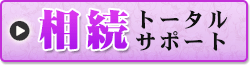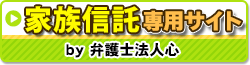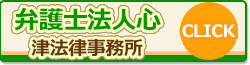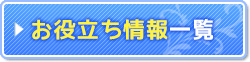適切な遺言作成のために
遺言書の形式や内容に注意しないと、思わぬ点で無効になったりトラブルが生じたりするおそれがあります。遺言作成をお考えの津の方も、参考までにQ&Aをご覧ください。
当法人へのご相談
津駅から徒歩0.5分の位置に、弁護士法人心 津法律事務所があります。フリーダイヤルやメールフォームにて受付を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言に強い専門家の探し方
1 遺言に強い専門家とは

遺言に強い専門家は、相続の法律問題や手続だけでなく、相続税にも強い専門家であると考えられます。
遺言では、誰がどの財産を引き継ぐかを決めることとなります。
そして、誰がどの財産を引き継ぐかにより、課税される相続税が異なってくることがあります。
たとえば、相続税には、小規模宅地等の特例という特例があります。
小規模宅地等の特例を用いることができる場合には、土地の評価額を一定面積までは80%または50%減額することができます。
ただ、小規模宅地等の特例を用いることができるのは、一定の宅地を一定の相続人が引き継いだ場合に限られています。
たとえば、被相続人が居住していた宅地については、配偶者、同居親族、持家に居住していない親族(配偶者と同居親族がいない場合)が宅地を取得した場合に利用することができます。
このため、被相続人が居住していた宅地を取得するのが上記のいずれかでしたら、小規模宅地等の特例を利用することができますが、上記のいずれかに該当しない場合は、小規模宅地等の特例を利用することができません。
このように、被相続人が居住していた宅地を取得するのが誰であるかにより、小規模宅地等の特例を利用することができるかどうかが大きく異なってくることとなります。
専門家としては、小規模宅地等の特例を利用することができるかどうかを検討した上で、被相続人が居住していた宅地を誰が取得するかについて、アドバイスを行うことが求められる場面だと思います。
遺言について相談を行う場合には、相続税等の課税について、適切に助言することができる、遺言に強い専門家に相談したいところではあります。
このような専門家は、どのようにして探せば良いのでしょうか?
2 遺言に強い専門家の探し方
遺言に強い専門家と言えるためには、相続税の知識を有するとともに、誰がどのように財産を引き継げば税金がどのように変動するかについて、シミュレーションを行う能力が必要です。
このようなシミュレーションは、過去に相続税案件を多く取り扱っていなければ、困難であると考えられます。
過去に多くの案件を取り扱っていなければ、詳細な知識を身につけることは困難だと思われますし、財産の取得者等の条件を変更すれば、相続税額がどのように変動するかについて、見立てを行うことが困難であることが多いと考えられるためです。
このため、相続税に特化していることは、遺言に強い専門家の1つの要素になると考えられます。
最終的には、実際に相談を行い、専門家がどのようなアドバイスを行うかにより、シミュレーションを適切に行うことができる専門家かどうかを判断することにはなると思いますが、相続税に特化しているという点は、1つの目安にはなると思います。
遺言を作成する際に注意すること
1 自筆証書遺言を作成するときの注意点

遺言には、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が作成するものであり、専門的な知識に基づくチェックのもと作成されるものとなります。
他方、自筆証書遺言は、自筆で作成されるものとなります。
自筆証書遺言は、いつでも、どこでも作成できるというメリットがあるものの、専門的な知識に基づくチェックがなされずに作成されることがあり、後日、無効になってしまうおそれがあるものであると言えます。
このため、自筆証書遺言については、作成時に注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、自筆証書遺言を作成するときの注意点について、いくつか説明したいと思います。
2 全文を自書すること
自筆証書遺言を作成するときは、全文を自書する必要があります。
パソコン打ちした遺言や第三者が筆記したものは、遺言としては無効になってしまいます。
どれだけ長文のものであったとしても、全文を自書する必要があることとなります。
ただ、財産目録(財産の一覧表)については、近年の法改正により、自書したものでなくても良いこととなりました。
このため、財産目録に限っては、パソコン打ちしたり、第三者が筆記したりしたものであっても、有効であることとなります。
ただし、この場合には、財産目録の各ページに遺言者が署名、押印する必要があります。
3 作成の日付を自書し、署名、押印を行うこと
遺言には、作成日の日付を自書する必要があります。
作成日と異なる日付を記載すると、無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言には、自筆で署名し、作成者自身が押印する必要があります。
4 誰が作成したかを客観的に明らかにしておくこと
自筆証書遺言だけが残っている場合には、しばしば、本人が本当に作成したものかどうかが争われることがあります。
このような場合、筆跡鑑定を行えば、筆記した人が本当は誰であるのかを明らかにすることができると言われることがあります。
しかし、筆跡鑑定は、鑑定人の技量によって結論が左右されることがありますし、微妙な案件では、鑑定人の結論が大きく分かれてしまうこともあります。
このため、遺言を本人が作成したかどうかが争われた場合、後日、これを証明する手段がないという事態に陥ってしまうことがあります。
こうした事態になることを避けるためには、遺言を作成する時の動画や写真を残しておく、遺言に実印を押印し、印鑑証明書を添付する等の工夫を行った方が望ましいと言えます。
遺言を作成するメリット
1 遺言を作成する目的

遺言は何のために作成するのでしょうか?
多くの場合、遺言では、誰がどの財産を取得するかを定めます。
このように、あらかじめ、自身が亡くなった時点で所有している財産を、どのように引き継ぐかを決めておく目的で、遺言は作成されることとなります。
もっとも、あらかじめ、財産をどのように引き継ぐかを決めることにより発生するメリットは、ケースバイケースです。
ここでは、いくつかの場面について、遺言を作成しておくことにより生じるメリットを説明したいと思います。
2 相続人以外に財産を引き継ぎたい場合
遺言が作成されていなかったとすると、自身が亡くなった場合には、相続財産については、法律上の相続人が共有することとなります。
そして、法律上の相続人の間で、どの相続人がどの財産を引き継ぐかを話し合い、合意することとなります。
裏返せば、相続が発生した時点では、相続人以外の人は、相続財産については、何の権利も有していません。
このため、相続人以外の人が、直接、相続によって財産を取得することもできないこととなります。
相続人以外の人に財産を取得させたい場合には、一旦、相続人が財産を取得し、相続人以外の人に財産を売却するか、贈与する必要があることとなります。
しかし、このようなことを行うとなると、相続人に財産を売却、贈与することに同意してもらう必要があります。
しかも、財産を売却すると、譲渡所得税の課税がなされる可能性があり、財産を贈与すると、贈与税の課税がなされる可能性があります。
このように、相続人以外に財産を売却、贈与すると、相続の場面では納めなくても良かったはずの税金を納めなければならないこととなってしまいます。
これに対して、遺言を作成しておくと、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言に、「●●に財産を遺贈する」との定めを設けておけば、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができることとなります。
このようにすれば、遺贈するとの遺言の効力により、相続人の同意が得られなくても、相続財産を相続人以外の人に引き継ぐことができることとなります。
また、遺贈するとの遺言を作成しておけば、相続により財産を引き継いだこととなりますので、譲渡所得税や贈与税の課税もなされないこととなります。
このように、遺言を作成することにより、相続人以外の人に、相続財産を、確実に、税負担を軽減しつつ、引き継ぐことができます。
たとえば、相続人ではない親族に相続財産を引き継ぎたい場合、親族ではないものの、お世話になった人や団体に相続財産を引き継ぎたい場合には、遺言を作成しておく大きなメリットがあります。
内縁の配偶者や事実上の養子についても、法的には相続人ではありませんので、これらの人に相続財産を引き継ぎたい場合にも、遺言を作成しておく大きなメリットがあると言えます。
3 相続人に財産を引き継ぎたい場合①
前述のとおり、遺言が作成されていなかったとすると、相続財産については、法律上の相続人が共有し、法律上の相続人全員で、どの相続人がどの財産を引き継ぐかを話し合い、合意しなければなりません。
この合意は全員一致でなされる必要があります。
裏返せば、1人でも反対する相続人がいると、相続財産の引き継ぎを完了することはできません。
また、意思を表明することができない相続人がいる場合には、そもそも、話し合いを行うことができず、相続財産の引き継ぎを進めることができません。
他方、遺言を作成しておくと、相続人全員の合意がなかったとしても、遺言の効力により、誰がどの相続財産を引き継ぐのかが定まります。
相続人全員の意見が全員一致に至らなかったとしても、相続財産の引き継ぎを完了することができますし、そもそも、相続人全員による話し合いを行う必要すらないこととなります。
このように、遺言を作成しておくと、相続人全員による話し合い、合意を行わなくても、相続財産を引き継ぐことができます。
相続人間の意見対立が激しく、相続人全員の合意が期待できない場合には、遺言を作成しておくメリットが大きいと言えます。
また、行方不明の相続人がいたり、認知症等により判断能力を失った相続人がいたりする場合には、相続人全員による話し合いがそもそも不可能となりますので、この場合も、遺言を作成しておくメリットが大きいです。
4 相続人に財産を引き継ぎたい場合②
前述のとおり、遺言が作成されていなかったとすると、法律上の相続人全員で、どの相続人がどの財産を引き継ぐかを合意する必要があります。
それでは、相続人間の意見対立があり、合意ができなかった場合には、どのようなことが起きるのでしょうか?
この場合、家庭裁判所の手続により、相続分をベースとして、遺産分割の方法が確定されることとなります。
この場合の相続分は、生前贈与の有無(法律用語で言うと特別受益)や、被相続人の財産形成や身の回りの世話等への寄与の有無(法律用語で言うと寄与分)を考慮した、具体的相続分となります。
もっとも、相続人である以上、一定の権利は保証されていますし、特別受益や寄与分の主張も必ずしも認められるわけではないといった事情があるため、家庭裁判所の認定する具体的相続分は、被相続人自身が期待していたであろうものとかけはなれたものとなることが、ままあります。
つまり、家庭裁判所の手続によっては、本来、被相続人の生前の意思とは全く異なると考えられる具体的相続分が認定され、これにしたがって相続財産を分割しなければならないこととなってしまうことが起こり得るのです。
他方、遺言を作成しておくと、自身の意思で、どの相続人にどのような割合で相続財産を引き継ぐかを、一次的には、自由に定めることができます。
このような遺言の定めに対しては、遺留分の主張がなされることがあり、事後的に一定程度の修正がなされることがあります。
とはいえ、遺留分は、本来の相続分の半分程度であることが多いですので、遺留分の主張がなされたとしても、遺言を作成した意味が完全に失われるわけではありません。
このように、相続人間の相続財産の取得割合を修正したい場合には、遺言を作成しておくメリットがあります。
相続財産をできるだけ引き継がせたくない相続人がいる場合、相続財産を多めに引き継がせたい相続人がいる場合には、遺言を作成しておくメリットが大きいと言えます。
相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント
1 相続人が遺言で揉める理由

遺言を作成していたとしても、例えば、遺言が無効であるとの主張や遺留分侵害額請求の主張がなされ、揉めごとが生じるケースがあります。
このように相続人が遺言で揉める理由はいくつか考えられます。
まず、遺言による財産の分配が客観的に不公平である場合です。
その内容に不満を持った相続人との間で揉める可能性があります。
客観的な不公平があると、その是正を求めて法的な請求がなされる可能性があります。
次に、遺言による財産の配分が相続人にとって主観的に納得感の小さいものである場合です。
客観的に公平であったとしても、主観的な納得感が小さければ、不満が生じ、何らかの法的請求がなされる可能性も出てきます。
ここでは、それぞれの理由との関係で、相続人が揉めない遺言を作成するためのポイントを説明したいと思います。
2 配分の客観的公平性
配分の客観的な公平性の点からなされる主張で最も多いのが、遺留分侵害額請求です。
法律上、相続人は、相続財産について最低限保障された権利を有しており、これを遺留分といいます。
例えば全く財産を受け継がせないとなっていたケースなど、この遺留分が侵害されている場合、相続人は、遺言により財産を取得した人に対して遺留分侵害額請求権を行使し、一定の金銭の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額請求に対する対策としては、あらかじめ、権利主張をする可能性がある相続人に対し、遺留分に相当する財産を取得させることを、遺言で定めておくことが考えられます。
このように、あらかじめ、遺言で客観的な不公平を解消しておくことで、相続人同士の争いを回避できる可能性があります。
また、一見すると客観的に不公平な遺言であっても、このような遺言を作成した理由が明らかになり、相続人の主観的な納得感が得られるのであれば、相続人同士の揉めごとを回避できることがあります。
この点については、次で説明したいと思います。
3 配分の主観的な納得感
遺言による配分について、相続人の主観的な納得感を得るためには、なぜ、このような遺言が作成されたかを形に残しておくことが考えられます。
例えば、ある相続人が多額の生前贈与を受けているため、その相続人が遺言により取得する財産を減らすべき場合があります。
このような場合には、遺言の付言事項において、多額の生前贈与によって生じた不公平を解消するため、遺言で財産の配分を決めたことを明確にしておくことが考えられます。
また、録音やビデオレターにより、こうした説明を残しておくことも考えられます。
このような場面では、相続人であればこのような遺言を作成した理由は分かるはずだから、上記のような説明は残さず、遺言だけ作成すれば良いのではないかと考える方もいらっしゃいます。
しかし、実際には、相続人の揉めごとが発生すると、遺言を作成するに至った理由について相続人の共通の理解を得ることができず、紛争が激化してしまうことも多いです。
相続人の共通理解を形成するためにも、何らかの方法で、遺言を作成した理由を形に残しておくことが重要であるといえます。
遺言を作成する際にかかる費用
1 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言については、遺言を残す方が、全文、日付、氏名を自書し、押印すれば作成することができます。
このため、自筆証書遺言については、費用負担なく作成することが可能です。
なお、2020年7月10日からは、各地の法務局で、自筆証書遺言を保管することができるようになりました。
この保管制度を利用する場合、申請の際に3900円を支払う必要があります。
裏返せば、上記の手数料以外には、費用負担はありません。
このように、自筆証書遺言は、比較的安価で作成することができます。
もっとも、自筆証書遺言の記載内容は、遺言を作成する人自身が決めなければなりません。
このため、遺言を作成する人の考えで遺言を作成したものの、記載に不備があったため、相続後に遺言内容を実現できないといったことが起こり得ることとなります。
つまり、有効な自筆証書遺言を作成できるかどうかについて、遺言を作成する人が全面的にリスクを負うこととなります。
2 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人に希望する遺言内容を伝え、公証人が公正証書の形式で作成するものになります。
公正証書遺言を作成する際には、公証人に手数料を支払うこととなります。
公証人への手数料は、財産総額によって変動しますので、数万円のこともあれば、数十万円のこともあります。
公正証書遺言を作成する際には、法律上、2名の証人が立ち会う必要があります。
証人を準備することができないときは、公証役場に証人の手配を依頼することができますが、この場合、証人に対する謝礼として、1名あたり3000円から5000円程度の費用が必要になります。
公正証書遺言を作成する際には、基本的には、遺言を作成する人が公証役場まで行く必要があります。
もっとも、遺言を作成する人が介護施設に入所していたり、入院したりしており、公証役場まで行くことができない場合等には、公証人に介護施設や病院まで出張してもらうことができます。
このように、公証人が出張する場合には、公証人の日当(1万円から2万円)、交通費を支払う必要があります。
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言を作成しますので、記載の不備が生じるリスクは少ないです。
とはいえ、どのような内容の遺言を作成するかについては、遺言を作成する人の方で、あらかじめ決定しておく必要があります。
このように、遺言を作成する人が事前にどのような内容の遺言を作成するかを決めておいた上で、公証人との間で、記載についての打合せを行うこととなります。
3 専門家に依頼する場合
遺言を作成するにあたり、弁護士等の専門家に依頼する場合があります。
専門家に依頼した場合は、その専門家への費用も必要になりますが、以下のようなメリットがあります。
まず、自筆証書遺言の場合は、記載内容に不備が生じないよう、専門家から適切な助言を得ることができます。
公正証書遺言の場合も、どのような遺言を作成すれば紛争の回避や税金対策になるか等について、専門家からの助言を得ることができ、遺言の内容を専門家と協議して決めることができます。
こうしたメリットが得られるという観点から、遺言の作成について、専門家に依頼される方も多いです。
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者の役割

遺言執行者は、相続開始後に、遺言内容をきちんと実現する役割を果たす人のことをいいます。
この遺言執行者については、遺言で指定することができます。
遺言執行者は、就任すると、遺言内容の実現に向けて必要な行動を行います。
遺言執行者が行う行動は、おおむね以下のとおりです。
- ⑴ 各相続人に対し、遺言執行者に就任したことを通知するとともに、遺言書の写しを送付する。
- ⑵ 相続財産の調査を行い、遺産目録を作成する。
- ⑶ 遺産目録を各相続人に交付する。
- ⑷ 不動産の名義変更、預貯金の払戻、有価証券の売却手続き等を行う。
- ⑸ 遺言内容に従い、相続財産を配分する。
このように、遺言執行者が行うべき行動は様々です。
そして、遺言執行者が適切に行動しない場合には、相続人等から損害賠償請求がなされることもあります。
この点を踏まえると、遺言執行者は、誰でもよいというものではなく、適切に選ばなければならないことが分かります。
ここでは、どのようにして遺言執行者を選ぶべきか、説明したいと思います。
2 遺言執行者を選ぶ際のポイント
遺言執行者は、先に述べた手続きを行うことができる人であれば、誰でもなることができます。
相続人の1人が遺言執行者になってもいいですし、財産を取得する人が遺言執行者になってもいいです。
とはいえ、誰が遺言執行者になれば円滑に手続きを進めることができるかについては、検討が必要だと思います。
先述したとおり、遺言執行者は、各相続人に対して、遺言書の写しを送付したり、遺産目録を作成の上、送付したりします。
この過程で、相続人から、遺言の内容や相続財産の内容等について、問合せがある可能性があります。
場合によっては、遺言を不服とする相続人が遺言無効確認訴訟を提起することがあり、このとき、遺言執行者は、被告として訴訟対応をしなければならなくなることもあります。
これらが適切に行われなければ、遺言執行者は、相続人等から、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
以上の点を踏まえると、遺言執行者は、相続財産の調査や名義変更の手続きに精通し、ときには法的紛争に対処できる人が望ましいといえます。
専門家としては、これらの条件を満たすのは、弁護士以外にはありません。
このため、遺言執行者については、弁護士を指定するのが望ましいということができます。
どのような場合に遺言を作っておくべきか
1 遺言を作っておくとよいケース

遺言を作成する目的は、あらかじめ誰がどの財産を取得するかを決めておくことで、将来、相続の手続きをスムーズに行えるようにしておくことにあります。
遺言が存在しないと、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを合意する必要があります。
このような合意が成立しない限り、相続の手続きを進めることができず、不動産の名義変更や預貯金の払戻し、有価証券の売却もできないこととなってしまいます。
他方、遺言が存在すると、相続人全員で遺産分割協議を行ったり、合意しなかったりしたとしても、遺言に基づいて相続の手続きを進めることができるようになります。
以上を踏まえると、遺言を作っておくべきケースは、相続人全員で遺産分割協議を行ったり、合意を行ったりすることが困難であることが予想される場合であることとなります。
それでは、具体的にどのような場合が該当するのでしょうか。
以下では、この点についての説明を行いたいと思います。
2 相続人間の関係が悪化している場合
相続人間の関係が悪化している場合は、遺産分割協議を行ったとしても、合意に至ることが困難であることがあります。
どのような理由であっても、相続人全員が合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
このため、相続人間の関係が悪化している場合には、合理的な提案であっても、嫌がらせ目的で合意をしないといったことさえ起こり得るのです。
このため、相続人間の関係が悪化している場合には、遺言を作成し、遺言で相続手続きを行えるようにしておく必要性が大きいといえます。
3 相続人同士が疎遠になっている場合
相続人同士が疎遠になっている場合には、そもそも、遺産分割協議を行うことが困難であることがあります。
場合によっては、相続人が誰であるか、相続人がどこに住んでいるかさえ分からず、これらの調査から行わなければならないこともあります。
その上で、面識のない相続人に手紙を送付し、相続が発生したこと、相続財産について相続手続きを行わなければならないことを説明し、遺産分割協議に着手する必要があります。
こうした手順を踏むには、かなりの手間と時間が必要になります。
こうした事態を避けるためには、遺言で相続手続きを行えるようにしておくのが望ましいといえます。
遺言の種類
1 遺言には複数の種類がある

法律上、有効とされる遺言には複数の種類があります。
大別すると、普通方式と特別方式に分かれます。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
ここでは、それぞれの遺言について、概略を説明したいと思います。
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、財産目録を除く全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成する遺言です。
これらを遺言者自身が自書する必要がありますので、代筆やパソコン打ちされたものは、遺言にはあたらないこととなります。
また、実印でなくても構いませんが、必ず押印する必要があります。
相続開始後には、遺言書保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑があれば、すぐに作成することができます。
3 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人に口頭で遺言内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にすることにより作成されます。
公正証書の作成にあたっては、証人2名が立ち会う必要があります。
実務上は、あらかじめ、公証人と遺言の内容についての打合せを行っておき、当日は、公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者がこれを口頭で確認することにより、作成されることが多いです。
公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に手数料を支払う必要があります。
公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成されるものですので、後日、形式面で有効性が争われる可能性は低いといえます。
また、公証役場に遺言の原本が保管されますので、紛失のおそれもありません。
4 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、あらかじめ紙に遺言内容を記載し、署名、押印を行った上で、封印した状態にします。
これを公証役場に持ち込み、公証人と証人2名の立会いのもと、公証役場に保管を依頼します。
封印した状態で公正役場に持ち込まれますので、遺言内容を秘密にしておいたまま、公証役場に遺言を保管しておくことができます。
遺言内容については、自書する必要がなく、代書やパソコン打ちされたものでも構いません。
5 危急時遺言
危急時遺言は、疾病等の理由で、遺言者の死が迫っているときに限り、作成することができます。
証人3名の立会いのもと、遺言者が証人に口頭で遺言内容を伝え、証人が遺言内容を筆記した上で、各証人が筆記内容が正確であることを承認し、署名、押印します。
相続開始後には、必ず、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
6 隔絶地遺言
遺言者が伝染病で隔離されている場合、船舶内に隔離されている場合に作成することができる遺言です。
極めて特殊な場合に作成される遺言であり、現実には、ほとんど見かけることがないものになります。
遺言と遺留分について
1 遺言を作成したとしても遺留分の主張がなされることがある

遺言を作成すると、ひとまずは、遺言者が希望する人に対して、遺言者が希望する財産を引き継ぐことができます。
特定の人に対して、すべての財産を引き継ぐものとすることもできますし、特定の財産のみを引き継ぐものとすることもできます。
もっとも、法律上、相続人は、保障された最低限の権利として、遺言によって財産を取得した人に対して、遺留分を主張することができるとされています。
遺留分の主張がなされた場合には、遺言によって財産を取得した人は、相続人に対して、一定の金銭を支払わなければならなくなる可能性があります。
2 遺留分の主張がなされる心配がある場合の対応
遺留分の主張がなされる心配がある場合には、遺言者の側で、あらかじめ、一定の対策を取っておいた方が良い場合があります。
こうした場面では、どのような理由から、特定の人に財産を引き継ぐことを希望するのかというポイントに立ち返った方が良いでしょう。
⑴ 遺留分の主張がなされる例
例えば、他の相続人が多額の生前贈与を受けているため、生前贈与を受けていない相続人に財産を引き継がせたいという場合があるでしょう。
このような場合には、生前贈与を受けた相続人は、本来、生前贈与を受けた財産が遺留分から差し引かれることとなりますので、遺留分の主張を行うことができないはずです。
とはいえ、現実には、贈与契約書等の書類の証拠が残っていないと、遺留分侵害額請求がなされた段階で、他の相続人に対して生前贈与がなされていることを証明できない場合が多いです。
このため、他の相続人が、生前贈与を受けたことを秘して、遺留分の請求を行うと、これがそのまま認められてしまうこともあります。
⑵ 対策方法
このような場合には、どのような対策をとるべきなのでしょうか。
1つの対策として、遺言者が、遺言を作成するだけでなく、他の相続人に対して生前贈与を行ったことを証明できる証拠も残しておくことが考えられます。
この点、遺言者が、他の相続人に対する生前贈与について、時期、金額、贈与した理由等を記載した書面を残しておくと、生前贈与が存在したことを証明する証拠になる可能性があります。
形式としては、遺言に、他の相続人に対する生前贈与が存在することを理由として、特定の人に財産を引き継がせることを希望することを記載するとともに、生前贈与の時期、金額、贈与した理由等を記載することが考えられます。
3 遺言についてのご相談
このように、遺言を作成するにあたっては、遺留分を念頭に置いて、一定の対策をとっておいた方が良いことがあります。
遺言についてのご相談がありましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。
遺言を作成するタイミング
1 できるだけ早く作成することをおすすめします

遺言については、いずれ作成すれば良いと、現時点ではまだ何もしていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言は緊急性のないものですので、一見すると、いつ作成しても良いという印象を持たれる方が多いのではないかと思います。
しかし、実際には、遺言は、すぐにでも作成した方が良いといえます。
ここでは、その理由について説明したいと思います。
2 相続における遺言の影響力は極めて大きい
相続における遺言の影響力は極めて大きいです。
遺言がなければ、すぐに相続の手続を行うことはできませんが、遺言があれば、一定の書類を集めるだけで、すぐに相続の手続を行うことが可能になります。
また、遺言がない場合、他の相続人が権利主張を行うのであれば、相続分をベースとする分割を行うことをやむなくされます。
他方、遺言がある場合、他の相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができますが、権利割合は、おおむね相続分の半分程度になります。
つまり、遺言があれば、権利主張を行う相続人に渡すべき財産が、おおむね半分程度で済むこととなります。
このように、遺言の有無次第で、相続の結論が大きく変わってくる可能性があります。
3 タイミングを逃すと遺言の作成は不可能になる
遺言の作成はタイミングを逃すと不可能になってしまいます。
思いがけず遺言を作成する前に相続が発生してしまうと、取り返しのつかない事態になってしまいます。
また、遺言を作成する前に認知症が重度化してしまっても、遺言の作成はもはや不可能になってしまいます。
このように、タイミングを逃してしまったがために、遺言がない前提で相続を進めざるを得ず、他の相続人に相続分に相当する額の財産を渡すことをやむなくされる例は、非常に多いです。
4 遺言を作成すべき時期
以上から、遺言については、できるだけ早い時期に作成するのが望ましいでしょう。
例えば、遺言に関心を持ったら、すぐに作成するのが良いとさえ言えます。
このように、遺言に関心を持たれましたら、一度、専門家にご相談いただくのが良いのではないかと思います。
遺言に強い弁護士に相談すべき理由
1 遺言の落とし穴

遺言が実際に効果を発揮するのは、遺言を書いた人自身が亡くなった後のことになります。
このため、遺言が効果を発揮する段階で、遺言に不備があり、遺言内容を実現することができないことが判明した場合には、遺言を作成し直すこともできず、取り返しのつかない事態になってしまいます。
このため、遺言については、他の法的文書と比較しても、慎重に、不備のないものを作成すべき必要性が高いと言うことができます。
万全を期して不備のない遺言を作成するため、遺言案の作成について、法律の専門家である弁護士に相談される方は多いです。
遺言案の作成については、どの弁護士に頼んでも同じであるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
実際には、遺言案については、遺言に強い弁護士が作成するかどうかによって、大きく異なってくることがあります。
遺言については、専門家であっても陥りかねない、思わぬ落とし穴がいたるところに潜んでいるからです。
以下では、こうした遺言の落とし穴の例について触れることとし、遺言に強い弁護士に相談すべきであることを説明したいと思います。
2 遺言執行者が判断能力を失っていた例
この事例では、弁護士と公証人の関与のもと、遺言者が配偶者にすべての財産を相続させるとの内容の公正証書遺言が作成されていました。
また、公正証書遺言では、財産を受け取る予定だった配偶者が、遺言執行者に指定されていました。
遺言執行者は、遺言内容の実現のため、相続財産の管理、処分を行う権限を有する人のことを言います。
遺言執行者が指定されると、基本的には、遺言執行者が金融機関や証券会社等の手続を行い、遺言内容の実現のための必要な行動を行うこととなります。
このように公正証書遺言の作成がなされた後、遺言者が亡くなり、遺言執行がなされることとなりました。
ところが、遺言者が亡くなった時点で、配偶者が重度の認知症に罹患していました。
このため、配偶者は、遺言執行の手続を行うことが一切できない状態になっていました。
遺言執行者に指定されていた人が遺言執行を行うことができない場合、別の遺言執行者を立てる必要があります。
そして、別の遺言執行者を立てるためには、家庭裁判所において、遺言執行者選任申立を行う必要があります。
遺言執行者選任申立の準備を行い、申立がなされ、家庭裁判所により遺言執行者の選任がなされるまで、何か月かの日数が必要となります。
この間、相続財産を動かすことはできず、遺言執行者の選任を待たなければならないこととなります。
また、誰が新たな遺言執行者に選任されるかは、家庭裁判所の判断に委ねられています。
専門家が遺言執行者に選任された場合には、専門家に対して報酬を支払わなければならず、当初、想定していなかった費用負担も生じることとなります。
こうした事態に陥ることを回避するためには、遺言で遺言執行者に指定された人が遺言執行を行うことができない場合は、他の人を遺言執行者に指定するといった規定を設けておく必要がありました。
このように、不測の事態を想定した遺言案を作成することができるかどうかは、弁護士によって分かれてくるところだと思います。
遺言について専門家に相談する際の流れ
1 遺言の種類

遺言は、多くの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかで作成されます。
自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、基本的には、全文を自書し、作成日付の記入、署名、押印を行って作成するものです。
公正証書遺言は、公証人が公正証書の形式で遺言を作成するものです。
どちらの遺言にするかによって相談する際の流れが異なってきますので、以下では、それぞれの流れについて説明を行いたいと思います。
2 自筆証書遺言の作成の流れ
自筆証書遺言を作成するにあたっては、事前に文案を作成し、文案のとおりに自書するという流れにした方が良いでしょう。
遺言については、わずかな文言の違いによって、相続の手続きができなくなってしまうことがあります。
このため、遺言を自筆で作成する際には、1つ1つの文言まで、細心の注意を払う必要があります。
そのためには、事前に、専門家と打合せを行い、文案を作成することをおすすめします。
文案が完成したら、そのとおりに遺言を作成することとなります。
そして、遺言が完成したら、再度専門家にチェックしてもらうのが安心です。
わずかな誤字でも、遺言で手続きができなくなる原因になるおそれがあるためです。
3 公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言を作成する際には、遺言を作成する方の戸籍、印鑑証明書、財産を取得する方の戸籍や住民票を準備し、これを公証役場に提出する必要があります。
まずは、これらの書類を準備するべきでしょう。
次に、遺言の文案を作成し、公証役場に提出すると、流れがスムーズになるかと思います。
公証役場で作成を希望する遺言の内容を聞き取ってもらい、公証役場で文案を作ってもらうことも考えられますが、その場合は公証役場との打合せを重ねる必要があります。
あらかじめ、専門家に遺言の文案を作ってもらい、これを公証役場に提出し、公正証書を作ってもらった方がスムーズに進むかと思います。
最後に、公証役場と日程調整を行い、その日に公証役場へ行き、公正証書の作成を行います。
公証役場では、念のため、人違いではないことの確認を行った後、遺言の内容を口頭で確認します。
このとき、遺言を作成する方の実印が必要になりますので、必ず持っていくようにしましょう。
遺言作成について依頼する場合の専門家の選び方
1 遺言の作成をお考えなら弁護士へ

遺言作成に関係する専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行等様々です。
もっとも、一口に専門家と言っても、すべてが適切な方法、適切な内容の遺言を作成できるわけではありません。
専門家にも、得意不得意がありますので、遺言作成に関する依頼を行うにあたっては、適切な専門家選びが必要になってきます。
それでは、専門家に遺言作成についての依頼をする場合、どの専門家に依頼するのが良いのでしょうか?
結論としては、以下の理由から、弁護士に依頼することをお勧めします。
2 法的知識に裏付けられた遺言の作成が期待できる
遺言には、思わぬところに落とし穴があります。
一度遺言を作成すると、これで安心してしまい、あえて作成済みの遺言をチェックしようとは思わない方が大多数だと思います。
このため、遺言に落とし穴が存在することが発覚するのは、多くの場合、遺言を作成した方が亡くなられたあとになります。
このような事態が生じた場合には、遺言内容を実現することができず、相続人全員での協議を行わざるを得ないことがあります。
協議の際に他の相続人が最大限の権利を主張してきた場合には、法定相続分での分割を行わざるを得ないこともあります。
ここでは、1つの事例を紹介したいと思います。
この事例では、子が2人いましたが、特定の子にすべての財産を相続させるとの遺言を作成されました。
このような遺言は、もう1人の子に一切の財産を取得させることを希望しない場合に、しばしば作成されます。
その後、すべての財産を相続させるものとされた子が、遺言を作成した人よりも先に亡くなってしまいました。
この場合、遺産は誰が取得することになるのでしょうか?
過去に同じような事例で争いが生じ、最高裁判所が判断を行ったことがあります。
最高裁判所は、原則として、遺言は効力を失うこととなり、遺産を取得しないはずだったもう1人の子が、法定相続分に基づく主張を行うことができるとの判断を行いました。
遺言を作成した方がもう1人の子に一切の財産を取得させることを希望していなかったのであれば、このような事態は、遺言を作成した方が全く希望していなかった事態に他なりません。
とはいえ、遺言を作成した方がすでに亡くなってしまっていると、こうした事態を避ける手段は、もはや存在しないことになってしまいます。
こうした事態を避けるためには、遺言を作成した方が存命のうちに、できれば、最初に遺言を作成した段階で、何らかの手立てを打っておく必要があります。
たとえば、すべての財産を相続させるものとされた特定の子が、遺言を作成した人よりも先に死亡した場合は、すべての財産を●●に相続させるといった内容の遺言を作成しておけば、こうした事態は避けることができます。
こうした法的リスクを避けるためには、きちんと法的知識に裏付けられた遺言を作成する必要があります。
この点では、弁護士であればこそ、法的知識に裏付けられた遺言を作成することができると言えます。
3 遺言執行にも最後まで対処できる
遺言では、遺言執行者の指定がなされることが、しばしばあります。
遺言執行者が存在すると、遺言執行者のみが、相続発生後に、遺言内容の実現のため、行動することができる地位を有することとなります。
その結果として、万一、他の相続人が協力的でなかったとしても、遺言執行者の権限により、遺言内容をきちんと実現することができます。
ここで注意しなければならないのは、遺言執行の場面で、紛争が発生することが予想される場合です。
職務上、法的紛争に対処することができるのは、弁護士だけです。
このことは、弁護士法において定められています。
また、弁護士以外の専門家は、基本的には、法的紛争への対処をほとんど行ったことがないというのが実情でしょう。
このような事情から、弁護士以外の専門家を遺言執行者に指定したとしても、相続発生後、紛争が顕在化すると、遺言執行者への就任を避ける行動に出てくる可能性があります。
その結果として、専門家に遺言作成に関する依頼をし、その専門家を遺言執行者に指定し、費用を支払ったものの、相続が開始した後になって、その専門家が遺言執行者に就任することを拒絶するといった事態が生じてしまうこととなります。
この点、弁護士を遺言執行者に指定すると、紛争性がある場合も含めて、遺言執行に最後まで対処することが期待できると言えます。