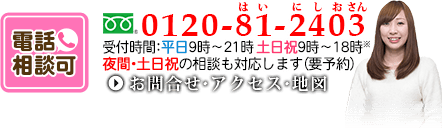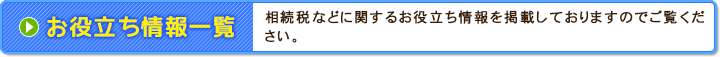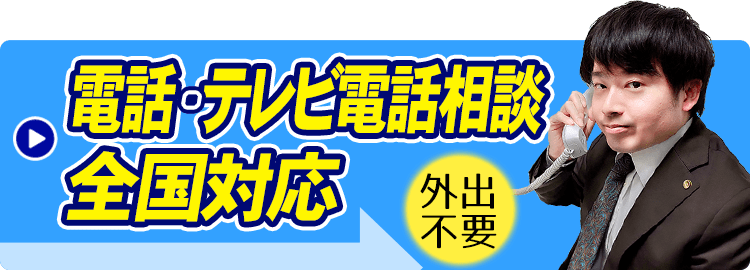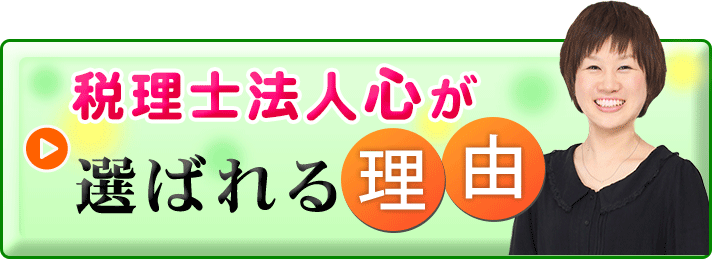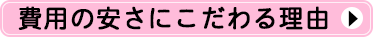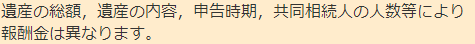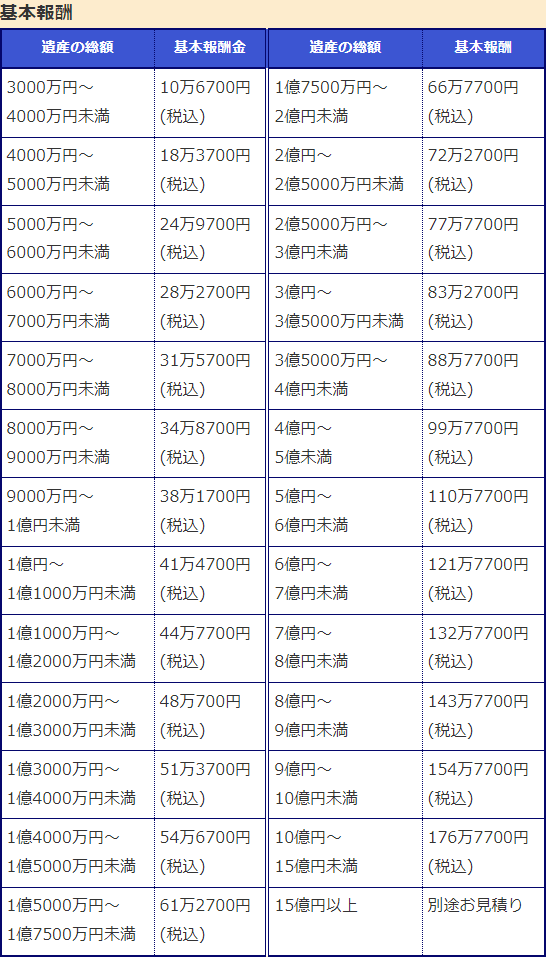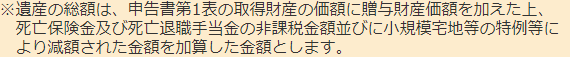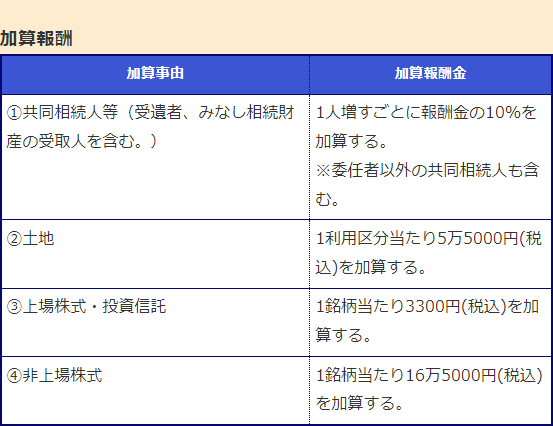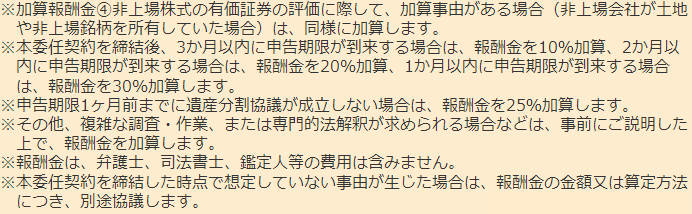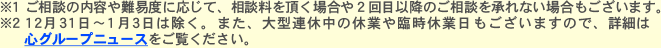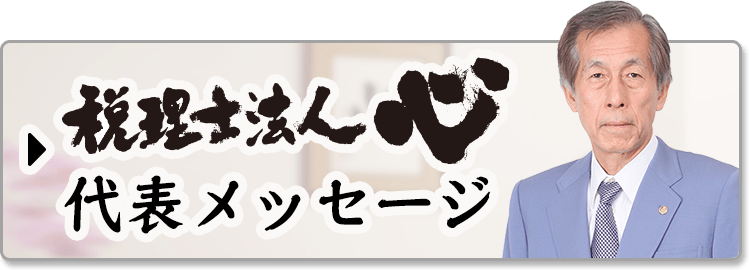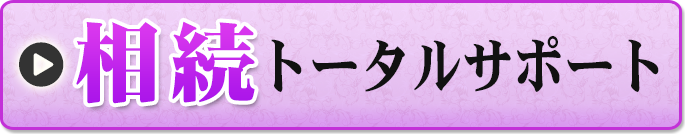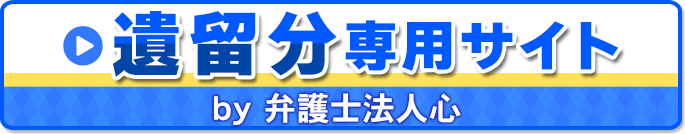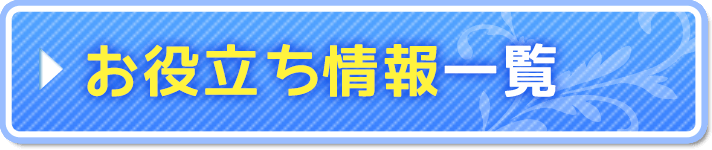二次相続に向けた相続税対策は、どのように行えばよいですか?
1 二次相続における相続税対策が必要になる理由
被相続人が亡くなり、配偶者と子が相続人となった場合を考えたいと思います。
また、この最初の相続を一次相続と呼びたいと思います。
一次相続での相続財産等の合計額が基礎控除額を超えると、相続税が発生することとなります。
このとき、配偶者に全部の相続財産や大部分の相続財産を引き継ぐこととすれば、相続税は課税されないか、大きく減額することができます。
というのも、配偶者の税額軽減の制度があり、配偶者が引き継いだ財産については、1億6000万円までは、相続税が課税されないこととなるからです。
また、配偶者が引き継いだ財産が1億6000万円を超える場合も、配偶者の法定相続分が1億6000万円を超えるときは、法定相続分までは、相続税は課税されないこととなります。
このように、配偶者には、大きな非課税枠がありますので、相続税の課税を避けるために、配偶者に全部または大部分の財産を引き継ぐこととすれば良いのではないかと考えがちです。
ただ、このような遺産分割の仕方には、大きな問題があります。
その後、配偶者が亡くなったときには、再び相続税の問題が発生することとなります。
この段階では、配偶者の税額軽減を使うことは、まずできません。
このため、相続財産は子が引き継ぐこととなり、相続税が課税されることとなります。
このように、配偶者が亡くなることで相続税が課税されることにより、二次相続での相続税の課税の問題が生じます。
そして、二次相続の段階では、法定相続人の人数が減りますので、一次相続よりも多額の相続税が発生しがちです。
相続税の基礎控除額(=相続税が課税されない財産額)は、3000万円+600万円×法定相続人数で計算されますが、法定相続人の人数が減少すると、基礎控除額も減少することとなるからです。
また、法定相続人の人数が減少すると、1人当たりの法定相続分額が増額することとなり、累進課税により適用される税率も増加することとなるからです。
このように、一次相続での相続税の減額を図った結果、かえって二次相続での相続税が増額されてしまう可能性が生じることとなるのです。
このように、二次相続の段階でより多額の相続税が課税される可能性が高いという問題に対処するためには、一次相続の段階で、二次相続での相続税も踏まえて、財産をどのように引き継ぐかを決定するのが望ましいということになります。
ここでは、二次相続に向けた相続税対策について、具体的に説明したいと思います。
2 一次相続で財産の一定割合を子に引き継ぐ対策
まず、一次相続で、財産の一定割合を子に引き継ぐ対策が考えられます。
一次相続で子に引き継いだ財産には、相続税が課税されることとなります。
この点だけ見ると、税負担は増えてしまいます。
しかし、配偶者にそのまま財産を引き継ぎ、二次相続でも相続税が課税されることとなると、法定相続人の人数が減少するため、基礎控除額の減少と相続税の税率の増加により、より多額の相続税が課税されることとなってしまいます。
このため、比較的、基礎控除額が大きく相続税の税率が小さい一次相続の段階で、子が財産を引き継ぎ、相続税をある程度納めてしまうという対策が有効になってくるのです。
他方で、一次相続の段階で子にすべての財産を引き継きでしまうのも考えものです。
試行的に、徐々に、一次相続で子が引き継ぐ財産の割合を増やし、配偶者が引き継ぐ財産を減らしていくことを思い浮かべます。
このようにすると、配偶者が二次相続の段階で有している財産は徐々に減少していくこととなります。
配偶者が有している財産が徐々に減少すると、相続税の税率も減少していくこととなります。
どこかで、一次相続での相続税の税率と二次相続での相続税の税率が逆転し、一次相続での税率の方が大きくなってしまうはずです。
このような状況下で、さらに一次相続で子に引き継ぐ財産を増やしたとしても、相続税対策としては有効ではないこととなります。
以上から、一次相続と二次相続の税率が逆転しない範囲で、子に財産を引き継ぐこととするのが、相続税対策としては有効であることとなります。
それでは、子に引き継ぐ財産が相続財産の何割まででしたら、一次相続と二次相続の税率は逆転しないのでしょうか?
この点は、被相続人が有している財産額、配偶者が有している財産額、一次相続から二次相続までの間の財産額の推移の予想によって、大きく異なってきます。
このため、各ご家庭の個別の事情を踏まえて、シミュレーションを行うことが必須になってきます。
3 一次相続で財産の全部または大部分を配偶者に引き継ぐ対策
次に、一次相続で、財産の全部または大部分を配偶者に引き継ぐ対策が考えられます。
先程と真逆のことを言っていますが、場合によっては、配偶者に財産の全部または大部分を引き継ぐ対策が有効になってきます。
配偶者がまだまだお元気であり、二次相続まである程度の時間がある場合は、配偶者に財産を引き継ぎ、二次相続までに十分に節税対策を取っておくという選択肢を取ることができます。
時間をかけて、配偶者の節税対策が功を奏することとなれば、二次相続の段階で課税される相続税を合理的に減少させることができます。
年単位で時間があれば、毎年、生前贈与を行うことにより、多額の財産を次の世代に移転することができます。
二次相続までまだまだ時間がある場合は、通常の暦年贈与での対策になりますが、7年以内に二次相続が発生する可能性があるときは、注意が必要です。
相続税は、相続開始日から遡って7年以内に、相続人に対して贈与された財産についても課税がなされます。
110万円以下の暦年贈与であり、贈与税が課税されない財産であっても、相続税については7年遡って課税がなされることとなります。
このように、子に対する暦年贈与については、二次相続が7年以内に発生する可能性がある場合は、相続税対策として意味をなさなくなる可能性があります。
このような場合は、子の側で相続時精算課税制度の選択肢届出を行うことにより、年間110万円までの贈与を、相続税の課税対象から除外することができます。
したがって、子に対する贈与については、相続時精算課税制度を利用することを検討すべき場合があります。
また、子や孫が住宅を新築または取得することを予定しているときは住宅取得資金贈与、死亡保険金の非課税枠が残っているときは生命保険の契約を行うことにより、短期間に非課税で財産を引き継ぐ準備をすることもできます。
住宅取得資金贈与は、制度改正が繰り返されてはいるものの、現時点では少なくとも500万円の財産を、贈与税も相続税も非課税で贈与することができます。
また、死亡保険金については、500万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないこととなっていますので、この非課税枠について使われていない部分があるのであれば、生命保険の契約を行うことも考えられます。
ただし、生命保険については、年齢、健康状態次第では契約ができない場合があります。
このように、二次相続までの時間がある場合は、あえて配偶者に財産を引き継ぎ、二次相続までに十分に節税対策を取っておくという対策も有効になってきます。
ビットコインなどの仮想通貨は相続税の対象になりますか? ゴルフ会員権を相続すると、相続税の課税対象になりますか?